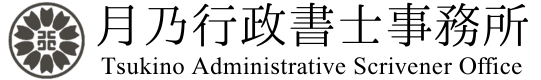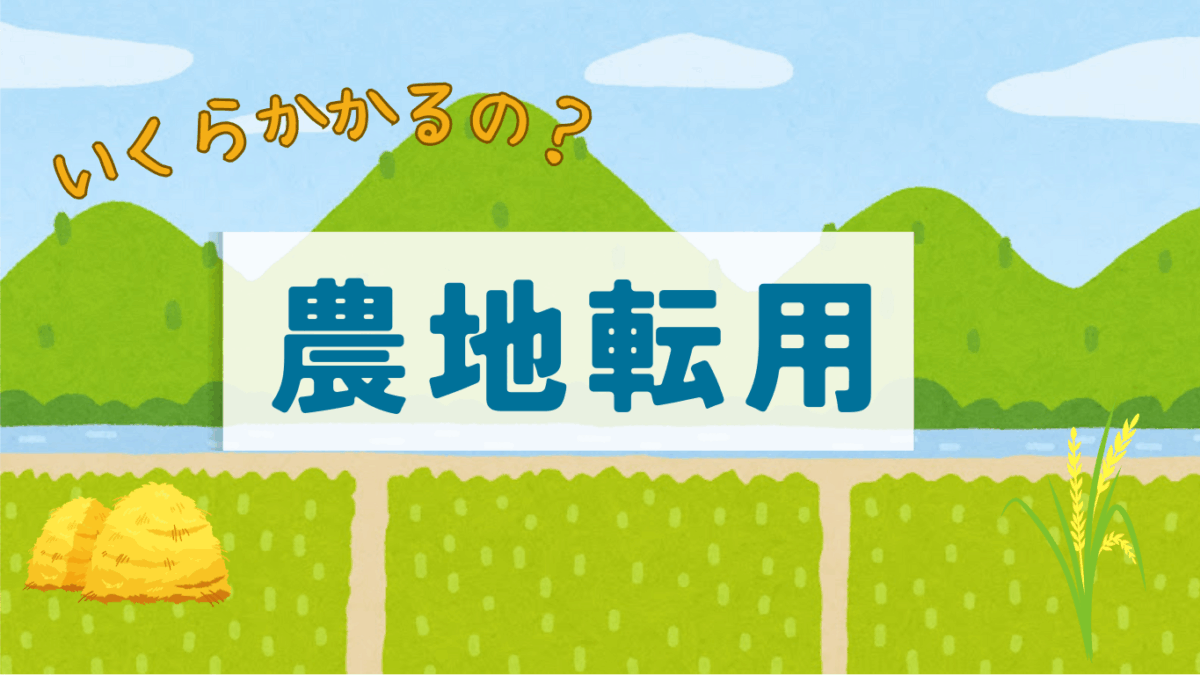農地を宅地や駐車場に転用する際、どのくらい費用がかかるのか気になる方は多いと思います。
農地転用では、転用許可申請、測量費用、登記費用、宅地造成やインフラ整備などさまざまな費用が発生します。専門家に依頼する必要があるかや面積や地域、転用目的によっても費用は大きく変わります。
宅地造成やインフラ整備、所有権移転登記などが必要なく、自分で手続きを全て行うなら、書類取得費用などの実費のみで、さほど費用はかかりませんが、専門家に依頼した場合には専門家への報酬が発生します。
この記事では、農地転用に必要となる費用の全体像をわかりやすく解説し、費用が変動する要因についてもまとめます。
農地転用にかかる費用の全体像
農地転用に必要となる全体の費用をまとめると、大きく5つに分けられます。
- 行政書士費用(農地転用許可申請代行)4万円~30万円
- 測量・境界確定・図面作成費用(土地家屋調査士)10万円~30万円
- 地目変更登記費用(土地家屋調査士)4万円~
- 所有権移転登記費用(司法書士)5万円~、+登録免許税(土地の評価額により異なる)
- 宅地造成・インフラ整備の工事費用(業者)数万円~数百万円
次はそれぞれの費用がいくらくらいかかるのか、個別に解説していきます。
農地転用許可申請・届出(行政書士費用)
農地転用の許可申請や届出を行政書士に依頼する場合の費用です。
目安としては4万〜30万円程度で、届出で済むのか、許可申請が必要なのか、作成する書類の量によっても報酬が変動します。
行政書士に依頼せず、自分で申請をするのであれば、この費用はかかりません。
測量・境界確定・図面作成(土地家屋調査士費用)
農地の境界を確定したり、申請用の図面を作成する費用です。
1区画あたり10万〜30万円程度が目安ですが、広さによっても変わりますので、土地家屋調査士へ見積もりを取りましょう。
既に整備されている土地であれば測量は必要ない可能性がありますが、一般的な農地だとどこからどこまでが該当の土地なのか、境界を正確に測っていないことが多くあります。これは後に近隣とのトラブルにも繋がりますし、後に行う地目変更登記でも必要となります。
また、農地の一部だけを宅地にしたい場合なども土地家屋調査士による測量が必要となります。境界が正確に分かっていて、農地の全部を転用する場合には測量が必要ない場合もあります。
地目変更登記費用(土地家屋調査士)
登記簿上の表題部に記載の地目を変更し登記する際にかかる費用です。地目変更登記は土地家屋調査士が行います。地目変更に登録免許税はかかりませんが、土地家屋調査士への報酬が発生します。数万円〜数十万円程度が目安です。

農地の場合、②地目部分に「畑」や「田」などと記載されています。宅地への変更登記をした場合には「宅地」と表記されます。
所有権移転登記費用(司法書士)
所有権移転登記は土地の所有者が変わる場合(売買や贈与等)に必要となり、司法書士が行うため、司法書士への報酬がかかるほか、国に払う登録免許税が必要です。
司法書士への報酬は数万円〜数十万円程度が目安となりますが、登記時に払う登録免許税は、固定資産税評価額によっていくら払うのかが変わってきますので、法務局に確認するか、司法書士に依頼する場合には司法書士に確認することをおすすめします。
工事費用(宅地造成・インフラ整備)
宅地造成や道路、水道・電気・下水などのインフラ整備にかかる費用です。
土地の面積や地形によって大きく変動し、数十万〜数百万円になることもあります。
現状が畑や田んぼの場合、宅地にするためには、整地・地均し・地固め、樹木の伐採、伐根が必要となりますし、田んぼの場合には地盤が弱くなっている可能性がありますので、地盤改良が必要となることもあります。
また、上下水道の引き込み工事や配管工事、電気・ガスの引き込み工事等が必要なこともあります。
農地を宅地にする際に必要となる工事費用の目安(100㎡あたり)
一般的な工事費用の目安をあげますが、あくまでも相場目安ですので、土地の状況(広さ、傾斜、インフラの有無)や地域差で大きく変動します。農地の状況によってどんな工事が必要になるのかが変わるため、工事業者に実際に見てもらって判断してもらう必要があります。
| 工事項目 | 内容 | 費用の目安(100㎡あたり) |
|---|---|---|
| 整地・地均し・地固め | 農地を宅地として利用できるように地面を平らにし、転圧で固める作業 | 約10万〜20万円 |
| 樹木の伐採・伐根 | 樹木や雑草を撤去し、根を取り除く作業 | 約5万〜15万円 |
| 地盤改良 | 軟弱地盤の場合に、柱状改良や表層改良を行う | 約20万〜50万円 |
| 下水道引き込み | 公共下水道を敷地内に引き込む工事 | 約30万〜60万円 |
| 電気引き込み | 電柱から敷地内へ電線を引き込む工事(電柱が近い場合) | 約5万〜15万円 |
| ガス引き込み | 都市ガス本管から敷地内へガス管を引き込む工事 | 約20万〜40万円 |
農地転用にかかる費用が変動する要因
これまで解説した通り、農地転用にかかる費用は一律ではなく、土地の工事が必要か、手続きに専門家を使うのかによって大きく変動してきます。
面積
農地の面積が広いほど、測量・登記・工事にかかる費用は比例的に増加します。例えば、100㎡単位で見積もりを出す業者が多いため、500㎡であればおおむね5倍の費用を想定する必要があります。
農地の所在区域(市街化区域/市街化調整区域)
市街化区域内であれば農地転用の届出だけで済むことが多く、手続きも比較的スムーズですが、市街化調整区域では農業委員会の審査が厳しく、多くの書類の提出が求められ、許可が下りるまでの期間が長くなります。そのため、行政書士報酬や手続き関連の費用が増える傾向があります。
転用目的(住宅/駐車場/分譲)
駐車場にしたり、資材置き場にするなら、さほど工事費用もかからないと思われますが、住宅を建てる場合には地盤改良工事や上下水道の引き込み、電気の引き込みなどの工事が必要になることがあるため、工事費用が高額となる傾向があります。
また、分譲地として複数区画に分ける場合には、測量や造成工事が大規模になり、費用も高額になります。
専門家の報酬設定
農地転用手続きを専門家に依頼する場合、それぞれの手続きにおいて携わる士業が異なります。先に開設した通り、すべての手続きを専門家に任せるとなると、行政書士・土地家屋調査士・司法書士が必要となります。
農地転用にかかる費用は誰が負担するか
農地転用にかかる費用をだれが払うべきかは、特に決まっておらず、自由に決めることができます。下記は転用後の土地を使用する人によって負担者を決める場合の一例です。
- 地主が負担する場合:自分の土地を転用する場合
- 借地人が負担する場合:借地人が事業利用のために転用する場合
- 売買・相続時の費用分担:契約内容で負担者を決定
土地所有者自身が自分の家を建てて住む場合など、自分が使うのであれば自分で払う必要があります。よく質問があるのは、土地を売買する場合や、土地を他人に貸す場合に誰が農地転用の費用を負担するのか?という点です。
結論から申し上げると、誰が費用を負担すべきかは決まっていませんので、相手方と話し合って決める必要があります。
特に売買の場合は、事前によく契約内容を話し合って確認する必要があります。農地のまま売買するのか、宅地に変えてから売買するのか、この辺りはとても重要です。農地のまま売買するケースでも宅地にするための費用は誰が負担するのかを明確にしておく必要があります。
賃貸の場合には所有権の移転はありませんが、これも賃貸借契約の内容で宅地にするための費用をだれが払うのか明確にしておく必要があります。
まとめ
農地転用にかかる費用は、行政書士への報酬+土地家屋調査士(測量)費用+登記費用+工事費の合計で考える必要があります。特に高額になる可能性が高いものは工事費用ですが、いくつかの業者に見積もりをとって、計画的に進めることをおすすめします。
しかし、いくら計画を練っても、農地転用ができない土地であるなら意味がありませんので、まずは該当の農地が転用可能であることを確認することが重要です。土地の所在地を管轄している農業委員会に相談してみることをおすすめします。