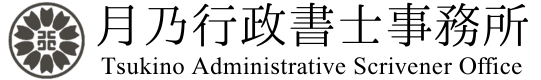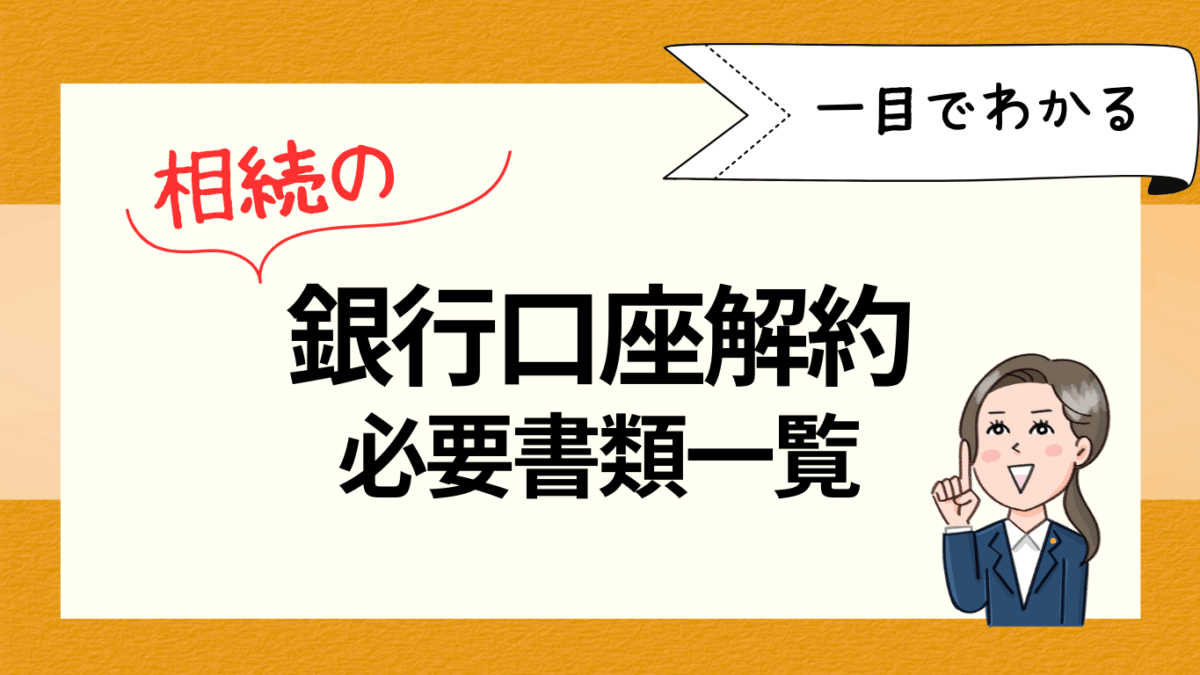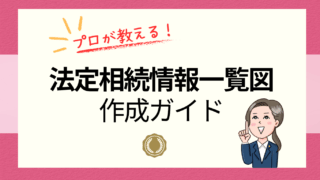ほとんどの方が銀行口座をお持ちだと思いますが、亡くなった方の銀行口座からお金を全額おろすには相続手続きをする必要があります。銀行口座の相続手続きは名義変更ができないため口座の解約手続きを行う形となります。
この記事では、相続時の銀行口座解約手続きに必要となる書類を分かりやすくシンプルに紹介します。
亡くなった人の銀行口座解約に必要な基本書類一覧
遺言書の有無や、遺産分割協議書の有無などによって、提出する書類に若干の変動はありますが、どこの銀行でも求められる基本的な書類は下記の通りです。
相続人の特定のため、亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。除籍謄本や改製原戸籍も含みます。
相続人の特定のため必要となります。最新の現在戸籍だけで足りることが多いです。
相続人全員の印鑑証明書はどの銀行でも求められます。
各銀行で指定している解約を依頼する書類です。
上記の1~2は法定相続情報があれば法定相続情報一枚で代用できます。
また、銀行の書式で相続関係図を書いて提出するよう求められることがありますが、法定相続情報一覧図があると、銀行指定書式の相続関係図の提出を省くことが可能となる銀行が多いため、銀行指定の書類を書く手間が省けます。
法定相続情報一覧図がある場合
法務局で認証をもらった原本の提出が必要です。
相続人全員の印鑑証明書はどの銀行でも求められます。
各銀行で指定している書類への記入が必要です。
法定相続情報一覧図を作成していると、戸籍謄本一式の提出が不要となるため、提出書類がとても減り、シンプルになります。遺産に銀行口座がたくさんある場合には法定相続情報一覧図を作成することをおすすめします。
遺言書がある場合の必要書類
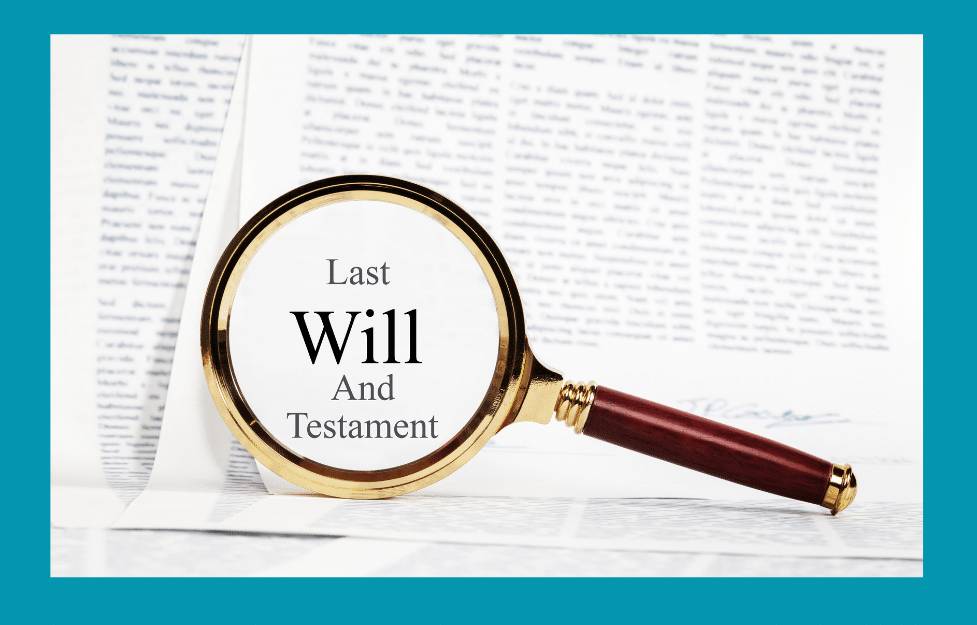
遺言書がある場合には、遺言執行者が指定されているかいないかで必要書類が若干変わってきます。
遺言書によって遺産をもらう人の事を「受遺者」と呼びますが、遺言執行者が指定されていない場合には、受遺者の戸籍謄本や印鑑証明書が必要となります。
遺言書は原本の提出を求められることが多く、公正証書遺言であれば正本か謄本、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所にて検認手続きがなされた原本(署名・捺印・日付の記載があるもの)を提出します。法務局の提供しているサービスである「自筆証書遺言保管制度」を利用した遺言書の場合には遺言書情報証明書の原本が必要となります。
遺言執行者が指定されていない場合の必要書類
相続人の特定のため、亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。除籍謄本や改製原戸籍も含みます。
最新の現在戸籍だけで足りることが多いです。
印鑑証明書はどの銀行でも求められます。
各銀行で指定している解約を依頼する書類です。
遺言書は原本が必要です。(法務局保管制度利用の場合は遺言書情報証明書の原本)
遺言執行者が指定されている場合の必要書類
遺言書に遺言執行者が指定されている場合には、受遺者の印鑑証明書に代わって、遺言執行者の印鑑証明書が必要になります。
相続人の特定のため、亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。除籍謄本や改製原戸籍も含みます。
省略できる場合もあります。
遺言執行者の印鑑証明書があれば受遺者の印鑑証明書は必要ないことが多いです。
各銀行で指定している解約を依頼する書類です。
遺言書は原本が必要です。(法務局保管制度利用の場合は遺言書情報証明書の原本)
遺言書がある場合にも、法定相続情報一覧図を戸籍謄本の代わりに使うことができます。受遺者が相続人以外の場合には受遺者の戸籍謄本の提出を求められることがあります。
遺産分割調停または審判後の手続き

家庭裁判所での遺産分割調停、審判を経て解約手続きを行う場合には、遺産分割調停調書や審判書謄本と確定証明書を提出する必要があります。
家庭裁判所にて発行される書類です。審判書謄本の内容によって審判確定証明書が必要になることがあります。
調停または審判で該当の預貯金を相続することが決まった人の印鑑証明書です。
各銀行で指定している解約を依頼する書類です。
通帳やカードを紛失した場合、解約できる?
結論から申し上げると、通帳やカードを紛失していても解約手続きは行えます。
通帳やカードが手元にある場合は銀行口座解約書類とともに銀行へ提出します。通帳やカードを紛失している場合はその旨を伝えれば解約手続きを行うことができます。
解約手続きをした後に通帳やカードが発見されても、使用することはできませんので、見つけ次第銀行に返却したほうが安心です。
相続における銀行口座解約手続きのながれ

必要書類についてご説明して参りました。必要書類が集まったら、実際に銀行に解約する手続きを取っていきます。一般的な手続きまでの流れをご紹介します。
銀行へ口座の所有者が亡くなったことを伝えます。
この連絡をすることで、解約手続きに必要となる書類を送ってもらえます。
銀行口座はこの段階で凍結されます。相続開始の連絡は窓口や電話、Webでも受け付けている銀行がありますが、銀行によって異なるため確認が必要です。
銀行所定の手続き書類が届きます。必要事項を記入し、必要書類とともに提出します。
郵送か窓口での手続きなのかは銀行によって変わります。
書類を提出してから2~3週間で相続人の銀行口座に払戻が完了します。
窓口での手続きしか受け付けていない銀行や、電話や郵送でも対応してくれる銀行など、各銀行で取り扱いが異なりますので、口座がある銀行に確認が必要です。
相続における銀行の解約手続き代行サービス
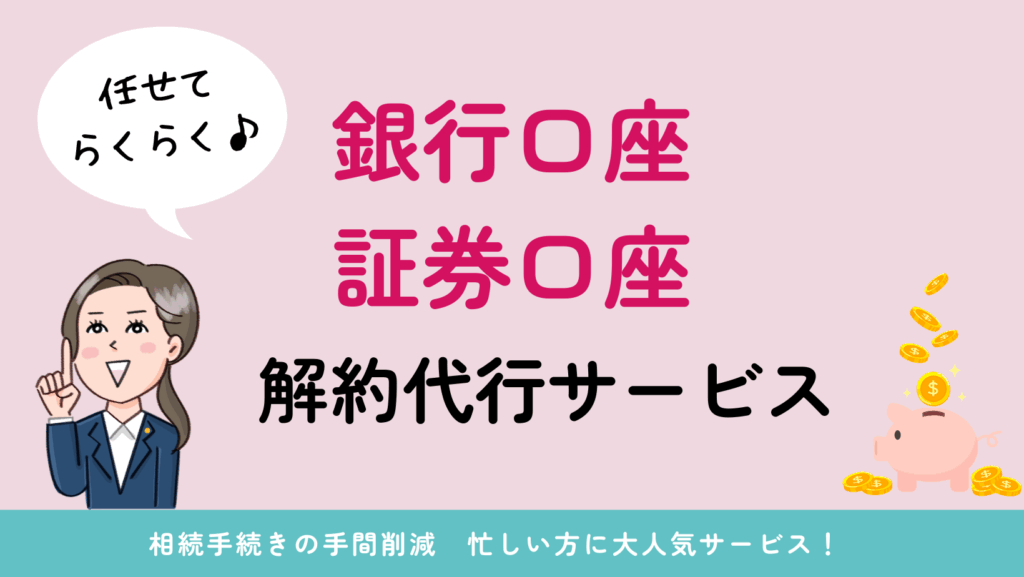
日中仕事をしている方には手続きを行う時間がなく、後回しになりがちな銀行解約手続きですが、弊所では相続の銀行解約手続きを代行して行うサービスを提供しております。忙しい方などに大変好評のサービスとなっておりますので、ご自分で手続きするのが難しい方や時間が取れずに悩んでいる方はお気軽にご相談ください。
銀行口座解約手続きは、書類が一通りそろっている方へご提供しているサービスです。書類がそろっていない場合には、その他のサービスと併用していただくご案内になることもございます。気になる方は一度ご相談ください。